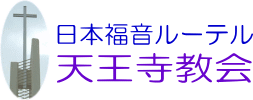MENU>>>|TOPページ|教会案内|今週の説教|教会への交通|教会学校|週 報|LINK | |
||
|
2025年8月31日 聖霊降臨後第12主日礼拝 「聖霊降臨後第12主日礼拝説教」
聖書日課第一日課 箴言 25章6節‐ 7節a 第二日課 ヘブライ人への手紙 13章1節‐ 8節, 15節‐ 16節 福音書 ルカによる福音書 14章1節、7節‐14節 【説教】 私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが、あなたがたにあるように。 私たちは、主の十字架の贖いにより神の御許に生きる約束を与えられています。それは、この贖いの御業によって、私たち一人ひとりが抱える罪の赦しを与えられているからにほかなりません。私たちが十字架を見上げる時、信仰によってそこに神のみ救い、赦しの御業を仰ぎ見、喜ぶと同時に、忘れてはならないのは、この主イエスの贖い、犠牲は、私の罪の為であったことを覚えることなのです。 この自分自身の罪、神に対して、隣人に対して、傷つけ、尊厳を踏みにじり、高慢になり、痛みを分かち合おうとせず、愛することができなかった自分自身の罪人の姿を見いださなければ十字架は救いとは成りえないと言っても過言ではないでしょう。つまり、主イエスの苦しむ御顔は、私の苦しみに悶える顔でもあるということです。 ですから、本質的に私たち一人ひとりは、御国における神の宴に集う資格もない存在でしかないのです。しかしながら、主イエスは罪人と食卓を共にしてくださいました。また、ザアカイの物語に示されてるように、罪深い者の悔い改めを受入れ、救いを宣言してくださいました。主イエスのご生涯において示されているように、招かれざる客と思われている罪人を招く方であることを顕しているのです。 私たちは罪人であるという真実に立つとき、主イエスが語られているように私たちは招いてくださった方に対して「お返しができない」存在でしかない。何故ならば、本来罪人の捧げるものを神はお喜びにならないからです。しかしながら、主イエスはあえてそのような人たちこそ招きなさいと教えるのは何故なのでしょうか。 それは、このことに神のお働きの真理が示されているからです。主なる神は、罪人を喜びの席に招いてくださっているということを示すわけですが、それはまず主イエスが、私たちの罪を贖うために十字架に架かって死んでくださったことによります。この主イエスの犠牲が、私たちの罪を赦し、婚宴の席に与からせるのです。 つまり、婚宴の席に際して私たちに送られた招待状は、主イエスの十字架であるということです。そうであるならば、私たちは何をお返しすればいいのでしょう。神である方が、ご自身の命を献げられた。それ以上のお返しを私たちは準備することはできないのは必然ではないでしょうか。だからこそ、私たちはただただ主イエスが、私の罪を贖って、神の救いに与るべき存在でない私を赦し、救いの喜びを分かち合う宴席に招いてくださっていることを感謝し、信じることしかできないのです。 そして、このたとえにおいて大切なことは何かというならば、「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」という御言葉に顕されています。「低くされ」「高められる」という言葉は、いわゆる受け身の形で表されている言葉です。つまり、低くなる、高くなるということは、自分自身によるのではなく、第三者が決めるということです。 この譬えで言えば、それは主人が決めるということであり、それは主なる神ご自身を示します。つまり、私たちを低くされるのも、高くされるのも主なのです。主が主権者であり、決定者なのです。私たちは、つい自分の地位や、社会的なものさしでどこに位置するかを自分自身で判断します。しかしながら、救いにおいては、私自身では決して決められないということをこの11節の御言葉が示します。 先ほど、私たちは、婚宴の席に招いてくださっていることを感謝し、信じることしかできないと言ったのは、このことによるのです。私たちの救いは、私たち自身の功績や業によるのではないのです。全ては神の御業であり、御国における祝宴に与るために私たちが成すべきことは、罪人であることを深く自覚し、神のみ前に悔い改め、神の救いの御業である主イエスの十字架を信じるほかないのです。 あれや、これやと私たちは何かをすることによって結果が与えられ、その人の評価や功績が決まるという社会の中に生きています。上座に座れないのは、あなたがサボったからだとか、技量が足りないからだ、財産が少ないから、生まれが悪いからだと言われるような社会の中に在って、人々は本当に疑心暗鬼になり、自己保存的になり、他者を罵り、傷つけ、陥れようとばかりしています。 その中で、聖書が伝えている普遍的なメッセージは、あなたの価値は、本質的には無であるということです。ゼロに何をかけてもゼロです。無である私に権威、地位、財産、知識、名誉をかけたとしても、私という存在の価値は神のみ前では無でしかない。そのことを私たちはわきまえなければならないと思うのです。 そのことを神は聖書の御言葉を通して示し、更には、その無価値な私たちのために神ご自身がお働きくださり、無である私たちを天に上げてくださり、祝宴に招いてくださっているという真実を伝えてくださっているのです。だからこそ、私たちは神のみ前に、そして隣人に対して謙り、仕えていく生き方をしていきたいと思うのです。 それはすでにルカ福音書6章で「32自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな恵みがあろうか。罪人でも、愛してくれる人を愛している。33また、自分によくしてくれる人に善いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。34返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ、同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。35しかし、あなたがたは敵を愛しなさい。人に善いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、いと高き方の子となる。いと高き方は、恩を知らない者にも悪人にも、情け深いからである。36あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい。」と教えられている通りです。 私たちは、愛に対して愛を返すことはもちろんですが、愛を返してもらう当てのない人をも愛しなさいと教えられています。それは主ご自身もまた主と敵対する者の前に謙り、己を低くして神の召しに従順になり、十字架の死さえも御身に引き取られました。謙るということは、相手を大切にし、愛するということです。この生き方に私たちは招かれているのです。 この世の誰かの評価によるのではなく、神が見ておられる。そして、その視線は普遍です。世の評価基準は、その時代時代、人によって変わります。しかし、私たちに向けられている本当の視線があり、私の言動をつぶさに聴いている方が居られることを覚えていきたいと思うのです。この神を軸として生きていくとき、私たちは本当に愛する者、憐れむ者、謙る者として歩むことが適うのではないでしょうか。このような生き方を歩むことができるように、この世の評価に左右されるのでも、自分の思いのままに生きるのでもなく、神の御言葉に聴いていく日々としていきたいと思うのです。 人知ではとうてい測り知ることのできない神の平安が、あなたがたの心と思いとを、キリスト・イエス にあって守るように。 |